- トップ
- トルコ
- ユダヤ
- テロ事件
- マイナンバ-
- TPP
- 難民・移民
- 株式市場
- 中国バブル崩壊
- 売上税
- 船員徴用
- ドイツ まとめ
- 警察 まとめ
- 格安まとめ
- 美術・絵画 更新なし
- 塩野七生 更新なし
- 4.1案 まとめ
- 艦船との衝突事故まとめ
- アンテイヒ−ロシリ−ズ まとめ
- 特攻 まとめ
- ヨットのための海の駅・泊地 まとめ
- 維新英傑 まとめ
- 幕末年表
- 筑前勤皇党
- 坂本龍馬 まとめ
- 高杉晋作まとめ
- 幕末芸州藩 まとめ
- 幕末開国 まとめ
- 北方領土 まとめ
- 韓国・朝鮮
- 拉致問題 まとめ
- 北朝鮮問題 まとめ
- 古楽
- 古楽器
- はやめ の 新バッハ全集
- ジョン・ダウランド全集
- ハインリッヒ・シュッツ全集
- コミンエルン まとめ
- 軍隊 と いじめ
- 安芸・廿日市まとめ
- モンテヴェルデイ全集
- 倉敷散歩
- 太平洋戦争 まとめ
- ヴェネツイアの音楽
- ヘンデル全集
- アトキンソン まとめ
はやめ
速魚の船中発策ブログ まとめ
新・所得倍増論
中小企業基本法
のんきな議論
「最低賃金引き上げ=中小企業倒産」の図式が神話に過ぎない理由
日本経済が「コロナ危機」にこれほど弱い根因
スペイン、イタリアと共通する「脆弱性」とは
追補
アトキンソン まとめ
もう忘れ去られたオランダ人のウオルフレン。しかし「説明責任」という言葉を残した。 グロ−バリズムで活躍した「大前研一」、もう生彩がない。 日本にその時代を先導したアナリストは多い。 今は個人的には「デ−ビット・アトキンス」が訴え掛ける。 京都の歴史ある企業の社長になった異色の青い目の外人であったが,それだけではなく活躍していると小生には思える。 ここに「まとめ」てみました。
2020-4-22
新・所得倍増論 デ−ビット・アトキンソン
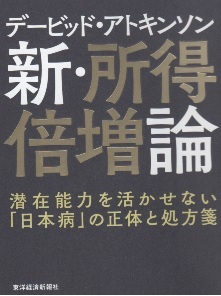
日本の文化財を修復する会社の青い目の社長をしているアトキンソンの著です。生き馬の目を抜く元ゴ−ルドマン・サックスのパ−トナ−まで務めた人でもあります。
日本の失われた10年と言っていたのが20年にもなり、アベノミクスの効果も上がっておりません。現在我が家の南側・東側に新築や建て替え工事が進捗中です、この町内でも新しい家が随分と増えました、低金利による建て替えブ−ムが起こっているようには見えますが、その程度では景気はビクともしません。根が深いといえます。
彼によるとGDP=人口x生産性であり、戦後に、奇跡の日本の躍進は爆発的な90年代までの人口膨張によるのであるといいます。 確かに日本の潜在的な能力は高いけれど、生産性は低くく、それに経営者の怠慢と人口ボ−ナスが減ったので、90年以降のGDPは停滞・縮小してきた。 また、過去の成功体験を間違った認識で理解して、見直せないのが現状のザマである。 現在生産性は先進国再開の世界27位である。
彼によれば、企業経営者に時価総額を上げる経営を要求すべし。確かに現在は株の40%余りを日銀が所有しています。そのことは健全な日本株市場ではありません。しかし、米英なみの会社時価に日本の会社株価が上がれば、国が多く所有していますので、その値上がりで、年金・医療は安泰になります。給料もあがります。よい循環になるでしょう。
先の大戦も軍部指導層の無能ゆえともいわれています。世界一優秀な下士官・兵でも負けました。 日本の優秀な知恵を集めた陸海士官学校出の将軍たちの及ぼした敗戦です。 日本の経営者が過去の戦後経済復興の成功体験に甘んじているとすれば、また歴史は繰り返すといったところでしょう。
この本はアカンタビリテイを知らしめたオランダ人の本に比べれば、すっきりした感が少ない個人的な印象です。大前研一さんが低欲望社会から提言されていますが、合わせて考えないといけないのかもしれません。こちらの能力を超えているようですが。
2017-1-20
ベイシックインカムをやるにしても現状を固定したままでは、新たな問題の創出に終わるのかもしれません。アトキンソンさん自身でまとめたものを出されていますので転載いたします。 小さな古い企業を再生させたに過ぎない人に大きな日本のことを改革できるわけがないと批判する人もいるようです。形式的なことで述べているだけで、彼の内容について具体的な議論を聞いたことはありません。考えはいろいろなので良い議論でさらに向上できるといいです。 福井モデルと関連してアトキンソンさんを読んでみるとおもしろい。
「中小企業基本法が諸悪の根源」
日本では法律の改正が行われると、改正前に存在したものは変えられることなく既得権として、以後もそれは存在します。 それはいつまでも改革されることなく存立していくことになります。 このことが一気に変革できなくて変われない日本ということです。 時限を区切ってでもそれを変えようとすることすらありません。
アトキンソンさんのいうように、競争力の無い企業が賃金を上げないということのみで存続して、いつまでも購買力が上がらず、30年間の停滞を招いたのでしょう。 この間に日本は1割の賃金低下、先進国は1.8倍の上昇。倍近くの差になったわけです。インバウンド盛況のこの頃ですが、かっての欧州におけるEC加入前のスペインと日本は同じ状態ですね。 すなわち、観光客が安くておいしい食べ物がある地スペインとして英国人・フランス・ドイツ人が訪れるわけです。 安くておいしい和食の地ニッポンです。 今では、 欧米のランチの価格を知るとびっくりします。それでは私たちはとても食べられません。 日本はこのような位置まで来てしまいました。

この法律が日本を「生産性が低すぎる国」にした
デービッド・アトキンソン 2019/10/03 07:30
https://toyokeizai.net/articles/-/305116 リンクが切れないように下記に転載させていただきました。
「町のラーメン屋が多すぎるといって10軒を1軒にまとめたところで中国には勝てません」
私の主張はまったく違います。今は10軒のラーメン店の裏に10社の企業があるので、10軒のラーメン店をそのままにして、それを所有している企業を2、3社にまとめようということです。
日本の生産性が低いのは「働き方」の問題ではない
さて、日本の生産性が一向に上がらず、デフレからも脱却できないという厳しい現実に対して、これは日本人に働き方に問題があるからだと主張する方たちが多くいらっしゃいます。
日本人はすばらしい能力をもっているのに、働き方が悪いのでその実力が引き出されていない。だから働き方を変えれば景気もよくなっていく、というのが彼らの主張です。
しかし、経済分析の世界では、これは「願望」というか、まったくの見当外れな分析だと言わざるをえません。これだけ大きな国の経済が「働き方」程度の問題によって、20年も停滞することなどありえないからです。
では、何が日本の生産性を低くさせているのでしょうか。これまで30年にわたって、日本経済を分析してきた私がたどり着いた結論は、「非効率な産業構造」です。高度経済成長期から引きずっている時代錯誤な産業政策、非効率なシステム、科学的ではない考え方などが日本の生産性を著しく低下させているのです。
ただ、日本国内ではこのような意見を掲げる人はほとんどいらっしゃいません。政治家、エコノミスト、財界のリーダーたちの大多数は経済低迷の要因を、「産業構造」に結びつけず、ひたすら「労働者」へと押し付けています。
このあまりに”残念な勘違い”を象徴しているのが、「働き方改革」です。
残業を減らし、有給休暇を増やす。女性にも高齢者にも、働きやすい環境を作る。そうすれば、労働者のモチベーションが上がって、これまで以上によく働く。その結果、会社の業績も上がるので景気がよくなる。
驚くほど楽観的というか、ご都合主義な考え方です。繰り返しますが、この程度の施策で巨大国家の経済が上向くのなら、日本はとうの昔にデフレから脱却しています。20年も経済成長が滞っているという事実こそが、労働者個人の頑張りでどうにかなる問題ではないことを雄弁に物語っているのです。
日本に欠けているのは「徹底した要因分析」だ
そこで次に疑問として浮かぶのは、なぜこうなってしまうのかということでしょう。なぜ表面的な経済議論しか行われないのか。なぜ国の舵取りをするリーダーや専門家から、泥縄的な解決策しか出てこないのか。
1つには、日本では「徹底的な要因分析」をしないという事情があります。この30年、多くの日本人と議論を交わして気づいたのは、経済の専門家を名乗る人たちでさえ、起きている現象についての知識はすごいものの、その原因を徹底的に追求することはほとんどありません。原因の説明は表面的な事実をなぞるだけで、「なんとなくこういう結論になるだろう」と直感的な分析をしているのです。
どういうことかわかっていただくため、多くの識者が唱える「女性活躍で生産性向上」という主張を例に出しましょう。
生産性の高い先進国では女性活躍が進んでいるという事実があります。一方、生産性の低い日本では、女性活躍が諸外国と比較して際立って進んでいないという、これまた動かしがたい事実があります。この2つの事実をもって、専門家たちは、日本も諸外国並に女性に活躍してもらえば、諸外国並に生産性が向上するに違いない、と主張しているのです。
確かにそういう理屈も成り立つかもしれませんが、実はここには大きな落とし穴があります。「日本の女性活躍が諸外国と比較して際立って進んでいない」ということの要因を分析できておらず、「日本は伝統的に女性が蔑視されている」「働きたくても保育所が不足している」という、なんとも大雑把な話しか語られていないのです。
このあたりの要因分析を徹底的に行えば、「保育所さえあれば女性が活躍できる」という極論がいかに表面的な分析に基づく主張かということは明白です。
海外の要因分析では、女性が活躍できていない国は、労働人口の中で、規模が小さくて経済合理性の低い企業で働く労働者の比率が高いという傾向があることがわかっています。
これは冷静に考えれば当たり前の話です。小さな企業は産休や育休、時短などの環境整備が難しいので、どうしても女性が働き続けることのハードルが高くなるのです。これが一次的な問題です。女性を蔑視する価値観や保育所の数などは、あくまで二次的な問題にすぎません。
当然ながら、まずは女性が活躍できる産業構造に変革した後で、具体的な環境作りに取り組むべきです。しかし、一次的な問題を解決せずに、二次的な問題を解決するだけでは、根本的な解決にはなりません。つまり、女性活躍というのは、女性蔑視うんぬんや保育所の数という二次的な問題より、その国の産業構造によって決まるというのが世界の常識なのです。
このような要因分析をロクにしないまま「女性活躍」を叫んで、働くように女性の背中を押しても、生産性向上につながるわけがありません。
これは同じく生産性向上が期待されている「有給休暇」についてもまったく同様です。
生産性が高い国では、有給休暇取得率が高い傾向があります。そして、日本は有給休暇取得率が低いということで、これを高めていけば、生産性も上がっていくだろうというわけです。しかしこれを本気で進めるのならば、そもそもなぜ日本の有給休暇取得率が低いのか徹底的に要因分析をしなくてはいけません。
日本では、「日本人の真面目な国民性が関係している」「日本は集団主義で職場に休みにくい雰囲気がある」と、これまた直感的な理由しか出てこないでしょうが、海外では「有給取得率は企業規模と関係する」という要因分析がなされています。大企業になればなるほど有給取得率が上がり、小さな会社になればなるほど下がることがわかっているのです。この傾向は万国共通で、日本も例外なく当てはまります。
つまり、アメリカの有給取得率が高いのはアメリカ人の国民性ではなく、単にアメリカの労働者の約50%が大企業で働いているから。日本の有給取得率が低いのも日本人の国民性ではなく、単に日本の労働者の中で大企業に勤めている人が約13%しかいないからなのです。
長く分析の世界にいた私からすれば、国民性うんぬん、労働文化うんぬんというのは、科学的な分析から目を背けて、自分たちの都合のいい結論へと誘導していく、卑劣な論法だと言わざるをえません。
日本の低迷の主因は伸びない中小企業
さて、このように日本の専門家があまりしてこなかった「要因分析」というものを、日本経済を低迷させている諸問題に対して行っていくと、驚くべきことがわかります。
実は日本経済の低迷も、女性活躍や有給取得率でもそうだったように、最後は必ず「小さな企業が多すぎる」という問題に突き当たるのです。低賃金、少子化、財政破綻、年金不足、最先端技術の普及の低さ、輸出小国、格差問題、貧困問題……さまざまな問題の諸悪の根源を容赦なくたどっていくと、「非効率な産業構造」という結論にいたるのです。
それはつまり、日本が他の先進国と比べて、経済効率の低い小さな企業で働く人の比率が圧倒的に多く、そのような小さな企業が国からも優遇されるということです。実は日本は、生産性の低い「中小企業天国」と呼べるような産業構造になっているのです。
このような話をすると、「小さな企業が多いのは日本の伝統で、普遍的な文化だ」とこれまた漠然とした主張をする人たちが多くいらっしゃいますが、実はこれも表面的な分析に基づく”残念な勘違い”なのです。
歴史を振り返れば、小さい企業が多いのは日本の普遍的な文化だと言えるような客観的事実はどこにも見当たりません。むしろ、ある時期を境にして、現在のような「他の先進国と比べて小さな企業で働く人の割合が多すぎる」という産業構造が出来上がっていったことがよくわかります。
では、その時期はいつかというと、「1964年」です。
この年、日本はOECD(経済協力開発機構)に加入しましたが、その条件として突きつけられたのが、かねてより要求されていた「資本の自由化」でした。当時の日本では、資本が自由化されれば外資に乗っ取られるかもしれないという脅威論が唱えられ、護送船団方式など「小さな企業」を守るシステムが続々と整備されました。つまり、1964年というのは、日本を「低生産性・低所得の国」にした「非効率な産業構造」が産声を上げたタイミングなのです。
日本を「生産性の低い国」にした中小企業基本法
そして、この「1964年体制」を法律面から支えたのが、前年に制定された中小企業基本法です。
同法は当時、「中小企業救済法」とも言われたほど、小さい企業に手厚い優遇策を示したものです。同時にその対象となる企業を絞り込むため、製造業は300人未満、小売業は50人未満とはじめて「中小企業」を定義しました。
しかし、これが逆効果となってしまいます。優遇措置を目当てに、50人未満の企業が爆発的に増えてしまったのです。
中には、企業規模を拡大できるにもかかわらず、優遇措置を受け続けたいということで、50人未満のラインを意図的に超えない中小企業まで現れてしまったのです。非効率な企業が爆発的に増え、なおかつ成長しないインセンティブまで与えてしまいました。
中小企業を応援して日本経済を元気にしようという精神からつくられた法律が、優遇に甘えられる「中小企業の壁」を築き、「他の先進国と比べて小さな企業で働く労働者の比率が多い」という非効率な産業構造を生み出してしまったという、なんとも皮肉な話なのです。
それでも1980年代までは人口が増加し続けたため、経済も成長を続けました。しかし1990年代に入り、人口増加が止まると、この生産性の低い非効率な産業構造の問題が一気に表面化してきました。
ちなみに、日本の生産性を議論する際に必ず出てくるのが、日本では製造業の生産性が高く、サービス業の生産性が低いという事実です。この現状を説明するためによく言われるのが「日本人はものづくりに向いている」「サービス産業の生産性が低いのは『おもてなし』の精神があるからだ」という”神話”のような話ですが、実はこれも非効率な産業構造ですべて説明ができます。これもまた、単に中小企業基本法の影響なのです。
この法律で、中小企業が製造業では300人未満、その他は50人未満と定義されて以降、日本ではこれに沿うような形で企業数が増えていきました。その影響もあって、製造業はどうしても他の業種よりも規模が大きくなりました。
規模が大きければ生産性が高くなるというのは、先ほども申し上げた経済学の鉄則のとおりです。一方、日本のサービス業は圧倒的に規模の小さな事業者が多く乱立しているという事実があるので、当然、生産性は顕著に低くなるというわけです。
「守りに特化」した経営は暴走していく
「1964年」と聞くと、ほとんどの日本人は東京オリンピックを連想すると思います。そしてここをきっかけに、日本人が自信を取り戻し、焼け野原から世界第2位の経済大国へと成長していく、というのが小学校の授業などでも習う「常識」です。
しかし、現実はそうではありません。
オリンピックの前年からすでに景気は減退していました。急速なインフラ投資の反動で、オリンピック後の倒産企業数は3倍にも急増しています。1964年からの「証券不況」も事態をさらに悪化させて、被害拡大防止のために日銀は公定歩合を1%以上下げました。しかしこれも焼け石に水で、1965年5月には山一證券への日銀特融を決定し、同年7月には、戦後初となる赤字国債の発行も行いました。
この不況が、「資本の自由化」が引き起こす「外資脅威論」にさらに拍車をかけます。「乗っ取り」や「植民地化」という言葉にヒステリックに反応するうち、やがて財閥系や大手銀行系が手を取り合い、買収防止策として企業同士の持ち合いも含めた安定株式比率を高めていきます。1973年度末の法人持株比率はなんと66.9%にも達しました。
この「守り」に特化した閉鎖的な経済活動が、護送船団方式や、仲間内で根回しして経営に文句を言わせない「しゃんしゃん株主総会」などを定着させて、日本企業のガバナンスを著しく低下させていったことに、異論を挟む方はいらっしゃらないのではないでしょうか。
このようにとにかく「会社を守る」ことが何をおいても優先されるようになると、経営者に必要なのは調整能力だけになっていきます。数字やサイエンスに基づく合理的な判断をしないので、他人の意見に耳を貸さず、とにかく「直感」で会社を経営するようになっていくのです。その暴走がバブルにつながります。
そんな「暴走経営」がこの20年、日本経済に与えたダメージは計り知れません。
ものづくりメーカーは、社会のニーズや消費者の声よりも、企業側の「技術」や「品質」という直感が正しいと考える「product out」にとらわれ衰退しました。そしてバブル崩壊後も、データに基づいた客観的な分析をせず、直感に基づく表面的な分析をして抜本的な改革ができなかった結果が、この「失われた20年」なのです。
このように日本経済の衰退を要因分析していくと、「1964年体制」に原因があることは明白です。つまり、「1964年は東京オリンピックで日本の飛躍が始まった年」というのは残念ながら間違いで、実は経済の衰退をスタートさせてしまった「国運の分岐点」なのです。
「1964年体制」がつくった産業構造を元に戻すことは容易なことではありません。その動かぬ証が、1990年代から実行されたさまざまな日本の改革がことごとく失敗してきたという事実です。その結果、国の借金は1200兆円にまで膨らみました。
人口減少などさまざまな「危機」が迫る日本には、もはや悠長なことを言っている時間はありません。日本経済を立て直すためにも、古い常識や”神話”を捨てて、数字と事実に基づく要因分析を、すべての国民が受け入れる時期にさしかかっているのです。
2019-10-16
日本人の 議論は「のんき」すぎてお話にならない 危機感 をもって「本質」を徹底的に追求せよ

デ−ビット・アトキンソン
経済規模を示すGDPは、「GDP=人間の数(つまり人口)×1人当たりの生産性」という式で表すことができます。これから日本では人口が減るので、生産性を上げないと経済の規模が縮小していきます。これは、かけ算さえ知っていれば誰にでも理解できる簡単な事実です。
人口が減っても高齢者の数は減らないので、年金や医療費をはじめとした社会保障費の負担は減りません。そのため、日本の場合、経済規模を縮小させてしまうことは絶対に許されないのです。
生産性を上げるとは、労働者の給料を上げること、そのものです。人件費をGDPで割れば、労働分配率が求められます。つまり、生産性と労働者の給料は表裏一体なのです。
英国銀行は、労働分配率を下げるとデフレ圧力がかかると分析しているので、デフレを早期に脱却するという意味でも、日本は労働者の給料を上げ、労働分配率を高めるべきです。
生産性向上にコミットする経済政策を「High road capitalism」と言います。「王道」と訳されることもありますが、見方を変えれば「茨の道」とも言えます。当然、その反対は「Low road capitalism」です。こちらは、ある意味で「邪道」とも言えます。
経済の「王道」と「邪道」
簡単に言うと「High road capitalism」は高生産性・高所得の経済モデルです。「High road capitalism」の根本的な哲学は「価値の競争」です。市場を細かく分けて、セグメントごとにカスタマイズされた商品やサービスで競い合うのが競争原理になります。そのため、商品とサービスの種類が多く、価格設定も細かく分かれています。
High road capitalismを志向している企業は、商品をいかに安く作るかよりも、作るものの品質や価値により重きを置く戦略をとります。他社の商品にはない差別化要素であったり、機能面の優位性であったり、とりわけ、いかに効率よく付加価値を創出できるか、これを追求するのが経営の基本になります。
最も安いものではなく、ベストなものを作る。そのスタンスの裏には、顧客は自分のニーズにより合っているものに、プレミアムな価格を払ってくれるという信条が存在します。
High road capitalismを追求するには、もちろん最先端技術が不可欠です。そして、それを使いこなすために、労働者と経営者の高度な教育も必須になります。同時に機敏性の向上も絶対条件です。
「Low road capitalism」は1990年代以降、日本が実行してきた戦略です。規制緩和によって労働者の給料を下げ、下がった人件費分を使って強烈な価格競争を繰り広げてきました。
海外の学会では、Low road capitalismに移行すると、一時的には利益が増えると論じられています。しかし、Low road capitalismによって短期的に利益が増えるのは、技術を普及させるための設備投資が削られ、社員教育も不要になり、研究開発費も削減される、すなわち経費が減っているからにすぎません。Low road capitalismは先行投資を削っているだけなので、当然、明るい将来を迎えるのが難しくなります。まさに今の日本経済そのものです。 実は、「Low road capitalism」でも経済は成長します。しかしそのためには、人口が増加していることが条件になります。人口が減少していると、「Low road capitalism」では経済は成長しません。本来「Low road capitalism」は、他に選択肢のない途上国がとるべき戦略です。先進国である日本は「High road capitalism」を目指すべきだったのです。なぜならば、「High road capitalism」こそが、人口減少・高齢化社会に対応可能な経済モデルだからです。
日本は「のんきな議論」が多すぎる
今回の記事にはあえて挑発的なタイトルをつけました。このタイトルは、ある意味、私のフラストレーションの表れかもしれません。 それは、今の日本で交わされている議論は日本経済についての現状検証があまりにも浅く、当然それによって、政策は本質を追求できていない、対症療法的なものになってしまっているという印象を強くもっているからです。
先週の「日本人の『教育改革論』がいつも的外れなワケ」でも若干触れましたが、人口減少にどう立ち向かうべきかについて、日本で行われている議論の多くは本当に幼稚です。今日本が直面している人口の激減は、誰がどう考えても、明治維新よりはるかに大変な事態で、対処の仕方を間違えれば日本経済に致命的なダメージを与えかねない一大事です。 それほど大変な状況に直面しているというのに、日本での議論はなんとも「のんき」で、危機感を覚えているようにはまったく思えません。こういう議論を聞いていると、正直、どうかしているのではないかとすら思います。
「のんきな議論」は、日本社会のありとあらゆる場面で見ることができます。
のんきな「競争力」の議論
先日あるところで、最低賃金を引き上げる重要性を訴えていたところ、「最低賃金を引き上げると日本の国際競争力が低下するからダメだ」と言われました。ちょっと考えるだけで、この指摘がいかに浅いかわかります。
日本の対GDP比輸出比率ランキングは世界133位です。輸出小国ですから、限られた分野以外では、別に国際的に激しい競争などしていません。また、他の先進国の最低賃金はすでに日本の1.5倍くらいですから、同程度に引き上げたとして、なぜ国際競争力で負けるかわかりません。さらに、多くの労働者が最低賃金で働いている業種は宿泊や流通などサービス業ですので、輸出とはあまり関係がありません。いかにも議論が軽いのです。
のんきな「教育」の議論
教育についての議論も、実にのんきです。教育の対象を子どもから社会人に大胆に変更しなくてはいけないのに、日本の大学はいまだに、毎年数が少なくなる子どもの奪い合いに熱中しています。 教育の無償化に関しても同様の印象を感じます。「子どもを育てるコストが高い。だから子どもを産まない、つまり少子化が進んでしまっている。ならば、教育のコストを無償にすれば、少子化は止められる」。おそらくこんなことを考えて、教育の無償化に突き進んでいるのでしょう。確かに、この理屈はもっともらしく聞こえなくもありません。 しかし、これは小手先の対症療法的な政策にすぎません。教育のコストが高いのが問題だから、無償化するという考え方も可能ではありますが、そもそもなぜ教育のコストを高いと感じる人が多いのか。その原因を考えれば、「収入が足りていない」という根本的な原因を探り出すことができます。
教育の無償化と、国民の収入アップ。どちらを先に進めるべきか、答えは収入アップに決まっています。要するに、少子化問題の本質は教育費にあるのか、親の収入が足りないのかを、きちんと見極める必要があるのです。 事実、日本人の給料は、同程度の生産性を上げている他の先進国の7割程度です(購買力調整済み)。なおかつ長年、若い人を中心に減少の一途をたどっています。問題の本質は教育費ではなく、給料なのです。
先進国の中では、少子化と生産性との間にかなり強い相関関係があるという研究があります。生産性が低く少子化が進んでいる複数の国で、教育費の補助を出しても思い通りには出生率が上がらなかったという興味深い事実もあります。 ですから、教育費を無償にしても本質的な対処にはなりませんし、税金か借金でまかなうしかないので、結局経済に悪影響を及ぼすのです。
のんきな「輸出」の議論
JETROの輸出促進とクールジャパンも同じです。問題の本質が分析できていないと思います。 私の分析では、日本が輸出小国である最大の理由は、規模が小さい企業が多すぎて、たとえすばらしい商品があったとしても、輸出するためのノウハウや人材が欠けている会社が大半だからです。 すなわち、輸出のためのインフラが弱すぎるのです(「ものづくり大国」日本の輸出が少なすぎる理由)。「日本にはいい商品はあるが、輸出は進んでいない。輸出をすれば国が栄えるから、輸出を応援しよう」。おそらくJETROが設立された背景には、こんな思考回路があったように思います。 しかし、思惑通りには輸出は増えませんでした。なぜかというと、JETROの応援なしに、持続的に輸出ができる規模の企業があまりにも少ないからです。日本の産業構造が輸出できる体制になっていない以上、いくら補助金を出して、輸出できない企業が一時的に輸出できる形を作っても、継続的に輸出が増えるはずもないのです。
まだまだある日本の「のんき」な議論 のんきな「先端技術」信仰
最先端技術も同じです。去年、落合陽一さんの本を読みました。最先端技術に関しては、氏の主張に異論を唱えるつもりはありません。
しかし、落合さんの主張を見ていると、日本の産業構造自体に技術普及を阻む問題があることに言及していらっしゃらないことが気になります。
あまりにも規模の小さい企業が多すぎて、技術の普及が進まないだけではありません。残念ながら日本では、せっかくの最先端技術を活用する気も、活用するインセンティブも持たない企業が大半なので、落合さんの英知が幅広く役立てられることもないように思います。
経済産業省のやっていることも輸出の発想と同じです。最新技術を導入すれば、経済は伸びる。しかし、実際には技術はなかなか普及しない。小さい企業は最先端技術を導入するお金がない。「ならば!」ということで、技術導入のための補助金を出す。 これもまた対症療法です。なぜなら、大半の企業は規模があまりにも小さくて、その技術を活用するための規模もなければ、使える人材も、わかる人材もいません。先週の「日本人の『教育改革論』がいつも的外れなワケ」のように、社員教育が著しく少ないことも影響しています。
のんきな「生産性」の議論
先日、厚生労働省と打ち合わせをしたときに、最低賃金を上げるのに備えて、その負担を軽減するために、企業に生産性を向上させるための努力を促す目的で補助金が用意されたという話を聞きました。しかし、せっかくの補助金なのに、申請された金額は用意された金額の半分以下だったそうです。やはり、小さい企業は現状のままでいいという思いが強く、生産性向上など考えていないようです。
経産省も厚労省もまったく思慮が足りていません。分析が浅すぎるのです。 決して公言はしないでしょうが、経産省は「日本企業は、お金さえあれば最先端技術を導入したいと思っている」という前提に立っているようですが、これは事実と反します。何度も言いますが、そもそも日本企業は規模が小さいので、仮に最先端技術を導入したとしても、十分に活用できるとは思えません。 厚労省は、「最低賃金の引き上げの影響を受ける企業は当然、生産性を向上したがる」と思っているようですが、この仮説も根本的に間違っています。
最低賃金で働いている人の割合が高い企業は、そもそもまともな経営がされていないか、または根本的に存続意義がないに等しい会社が多いので、自ら生産性を向上させようなどという殊勝な考えなど持ち合わせていません。補助金以前の問題です。 そういった企業は、声高に訴えれば政府が守ってくれるとわかっていますので、生産性向上という「余計」な仕事をするインセンティブはないのです。
のんきな「財政政策」と「金融政策」 のんきな「財政」の議論
財政の議論も浅いと思います。消費税の引き上げも対症療法でしかありません。 ご存じのように、日本は人口が多く、人材評価も高い割にGDPが少ないです。一方、社会保障の負担が大変重くなっています。そこで、年金の支給を減らしたり、医療費の自己負担を増やして、国の負担を減らすべきだという議論も交わされています。政府は消費税を上げて、税収を増やそうとしています。 しかし、私に言わせれば、この2つの方法は、夢のない、いかにも日本的な現実論にすぎません。この政策は、将来の負担をまかなうために、現状の日本経済が生み出している所得に何%のどういった税金をかけたら計算が合うか、という形で議論されています。あたかも、税率以外の他の変数は変えることができないという前提が置かれている印象です。
先述した通り、日本の財政の問題は支出の問題でもなければ、税率の問題でもありません。日本の財政の根本的な問題は、課税所得があまりにも少ないことに尽きます。しかし日本の議論では、「所得は増やすことができる」という事実があまりにも軽視されています。
消費税は上げるべきかもしれませんが、その前に付加価値を高め、その分だけ給料を上げて、上げた分の一部を税金として徴収すれば、それだけでかなりの規模の税収アップになります。
のんきな「量的緩和」の議論
経済学の教科書には、いくつかの「インフレの原因」が列挙されています。モノとサービスの需要が相対的に増えること、通貨供給量の増加、円安、財政出動は典型的なインフレ要因です。賃金が増えることも、大きな要因の1つです。
経済の状況が通常通りならば、財政出動と円安誘導と金融政策で経済は回復します。いわゆる、「インフレは日本を救う」論理です。 しかし、この議論には大きな盲点があります。それは、日本のように給料が減って、人口も減り、消費意欲が低下する高齢化社会では、需要が構造的に減るということです。もはや「通常」の状態ではありません。
このような状況で、中小企業問題や給料が少なすぎる問題を無視し、金融緩和や円安政策を進めても、通常の効果は出ません(もちろん、やらないよりはマシでしょうが)。給料を徹底的に上げていかないと、金融政策や財政だけでは通常の効果は期待できないのです。 「インフレは日本を救う」というだけの議論は、問題の本質を見極めていない議論です。企業の規模と給料には強い関係がありますから、企業規模を拡大し、給料を高めて初めて、金融政策・財政政策が生きてくるのです。
あらゆる問題は「給料が少ない」ことに帰する
デフレ、輸出小国にとどまっている問題、年金問題、医療費問題、消費税、少子化、国の借金、女性活躍問題、格差の問題、技術の普及が進まない問題、ワーキングプア、子どもの貧困、などなど。これらの問題の根源にあるのは、すべて日本人がもらっている給料が少なすぎることです。
今の政策は、ほぼすべてがただの対症療法です。問題の本質が見えていない。それでは病気そのものを完治させることはできません。
では、どうするべきか。『日本人の勝算』にも書きましたし、本連載でも述べましたが、やるべきことは明確です。世界第4位と評価されている優秀な人材を使って、先進国最低、世界第28位の生産性を上げればいいのです。それだけです。それには、賃金を継続的に上げる必要があります。
このことを、大半の日本企業の経営者が理解しているとは思えませんし、自ら賃金を上げる気のない経営者が多いのも間違いないので、彼らの奮起を期待してもムダです。だとしたら、「High road capitalism」に移行させるために、最低賃金を毎年5%ずつ上げて、彼らに強制的に生産性を引き上げさせるしか方法は残されていません。 それにあわせて、労働者を集約し、企業の規模拡大を促進するべきです。たとえ給料を上げても、企業の規模拡大を追求しない、もしくは小さな企業を守ろうとする政策を実施してしまえば、政策が矛盾し、「High road capitalism」は夢と終わります。
生産性の向上ができない経営者は、増える一方の社会保障負担を捻出するだけの才能がないのです。潔く企業経営から撤退してもらいましょう。人手不足は当分続くので、労働者は才能のある経営者のところに行けばいいのです。
最低賃金の引き上げの話を出すと、必ず昨年の韓国で起きたバカげた失敗事例を引き合いに出す人が現れますが、韓国は一気に16.4%も引き上げたから失敗したのです。このことは、すでに何回も指摘しています。だからこそ、日本は毎年5%でいいのです。
また、最低賃金を引き上げると、中小企業は皆つぶれるという意見も必ず寄せられます。しかし、そういう意見を持つこと自体、頭を使っていない証拠だと思います。 すべての中小企業の労働者が最低賃金で働いているわけでもなければ、すべての企業の経営がギリギリなわけでもないので、最低賃金を引き上げたからといって、中小企業が大量に倒産することはありえません。
日本人労働者の生産性は、イギリス人などのヨーロッパの人々とそれほど大きく違いません。しかし、最低賃金はたったの7割に抑えられているのです。
人材評価が大手先進国トップの日本は、それを武器に、大手先進国トップクラスの賃金をもらい、再び経済を成長させる。この挑戦にトライするしか、日本に道は残されていません。 それには、中小企業を集約させること。ここに「日本人の勝算」があります。
東洋経済オンラインより転載
https://toyokeizai.net/articles/-/275028?page=6
2019-4-6
「最低賃金引き上げ=中小企業倒産」の図式が神話に過ぎない理由
ここで2013年に最賃を1000円に上げるように書いていて、2015年には1500円に改定しました。2019年の昨日あたりに報道では1000円をつける地域が実現したようです。
韓国ともめていますが、最低賃金の議論をするときに、今度は文大統領が実施した韓国での最賃値上げの効用を日本の議論のなかに持ち込まれることになりそうです。法治国家でもない隣国のことはどうでもよいのですが、最賃に反対する人々は必ずまな板の上にあげるでしょうから、考えておかねばなりません。 イギリスでこれを研究検討されたレポ−トのオリジナルといっても翻訳されたものでしか取り込めない小生ですが、見つかればここに取り上げたいと思います。
増税後の買い物、お得になる払い方
最低賃金引き上げの議論で必ず出る「中小企業の倒産誘発論」だが、実はどこにもエビデンスはない
最低賃金引き上げを巡る論争が本格化し、様々な意見が飛び交っている。相変わらず「中小企業の経営が厳しくなる」と難色を示す人も多いが、実はイギリスでは最低賃金を引き上げても廃業率は上がらず、むしろ労働生産性が上がったとする調査結果が明らかになっている。(ノンフィクションライター 窪田順生)
最低賃金労働者は「無能」なのか?
いよいよ「最低賃金引き上げ」を巡る論争が本格化してきた。
さまざまな専門家の方がそれぞれの立場で意見をぶつけ合うということは、社会にとっても良いことなので、ぜひ侃々諤々でやっていただきたいところだが、頭の上をビュンビュンと飛び交う意見の中には、思わず二度見してしまうようなダイナミックなものも散見される。
例えば、“最低賃金引き上げ慎重派”の、とある著名な評論家の方。ざっくりまとめると、こんなことをおっしゃっていたのだ。
最低賃金で働いている人というのは、スキルが低いので一度職を失うと再就職ができない。最低賃金を上げることは結果として、こういう人を苦しめることになる。だから、最低賃金を引き上げて中小企業を倒産させるような愚かなことはするな、生産性向上のためには、低スキル労働者の教育に力を入れるべきだ――。
「ん?」と引っかかった人も多いのではないか。そう、確か日本は「深刻な人手不足」だったはずなのだ。コンビニはバイト確保ができず24時間営業もままならない。物流も深刻なドライバー不足で現場が疲弊している。建築や介護の現場にいたっては、外国人労働者に頼らないと回らない――という話になっていなかったか。
一方、平成27年の内閣府の資料には「最低賃金程度の時給で働く労働者は300万〜500万人程度」とあり、もっと多いという指摘もある。
つまり、この専門家の方は、日本人労働者の数%を「人手不足でもう限界だ!」と悲鳴を上げる事業者でさえも採用を見送るほど、「使えない人材」だとおっしゃっているのだ。
そんな考えをベースにして、最低賃金の引き上げは慎重にすべきと主張するというのは、中小企業はどこにも行くあてのない無能の人を雇ってあげている篤志家なんだから、「時給1000円」なんて無理難題を押し付けず、自分たちのペースでのんびりやらせてやれよ、と言わんばかりなのだ。
もちろん、立派な専門家センセイなので当然、我々素人には計り知れない深いお考えがあるのかもしれないが、素直に受け取れば「労働者ディスり」にしか聞こえない。なかなかシビれる発言ではある。
最低賃金引き上げは中小企業倒産につながらない
その一方で、ダイナミックというよりも、日本人にはなかなか受け入れがたいショッキングな提言をしている御仁もいる。
元ゴールドマン・サックスのアナリストで、山本七平賞受賞の「新・観光立国論」(東洋経済新報社)などで政府の観光推進政策にも多大な影響を与えてきたデービッド・アトキンソン氏である。
来日から30年にわたって日本経済を分析し、かつて日本の大手銀行が17もあって群雄割拠していたバブル期に、「日本の主要銀行は2〜4行しか必要ない」というレポートを出したこともある「慧眼」で知られているアトキンソン氏は、今の日本の低成長・低生産性を解決するには、最低賃金を年5%程度引き上げていくべきだとかねてから主張していたのだが、このたび発売された新著「国運の分岐点 中小企業改革で再び輝くか、中国の属国になるか」(講談社+α新書)でさらに驚くべき分析をしているのだ。
日本の現在の低成長は、国が“成長できない小さな企業”を手厚く保護する政策をスタートさせた「1964年体制」にあるとして、この古い体制を改革しないで放置していると、人口減少と自然災害というリスクの中で、日本経済が弱体化して、中国資本の支配力が強まっていくというのだ。
このあたりについて興味のある方はぜひ本をお読みいただくとして、実は同書の中には、現在の「最低賃金引き上げ」を巡る議論に一石投じるような記述があるのでご紹介したい。
それは、冒頭の専門家の方の主張にも通じるが、「最低賃金を引き上げたら倒産が増加して不況になる」という言説に対してものだ。以下に少し長いが、引用しよう。
「この20年間、最低賃金を引き上げ続けてきたイギリスでは、政府が大学に依頼して、賃金引き上げの影響を詳しく分析をしています。具体的には、最低賃金もしくはそれに近い賃金で雇用している割合の高い企業を対象にして、最低賃金を引き上げる前と、後の決算書を継続的に分析しているのです。そこで判明しているのは、もっとも影響を受けた企業群でも廃業率が上昇することはなく、単価を引き上げることもあまりなく、雇用を減らすこともなかったということです。そしてここがきわめて大事なポイントですが、経営の工夫と社員のモチベーション向上によって、労働生産性が上がったことが確認されているのです」(P.193)
要するに、「最低賃金を引き上げたら倒産が増加して不況になる」というこの手の議論で必ず出てくる言説は、科学的根拠のないデマだというのだ。
最低賃金引き上げに猛反発する日本の産業界
と聞くと、「イギリスは日本より格差が開いて、物価高で貧しい人が増えているぞ!そんな英政府の調査など信用できるか!」と噛み付く人もいるが、アトキンソン氏は別にイギリスが素晴らしいから日本も真似しろなどと言っているわけではなく、最低賃金引き上げの影響について国家レベルで調査が行われ、そこでは倒産につながらず、労働生産性が向上するという結果が出ている、と示しているだけにすぎない。「イギリスの貧しい人は日本より貧乏だぞ」みたいな感覚ベースの議論ではなく、科学的な議論をすべきだと言っているのだ。
また、イギリスにおける格差や貧困が問題だというが、実は貧困率は日本の方がアメリカと並んで先進国で最悪レベルで、イギリスよりもダントツに高い。格差や貧困がある国のエビデンスなんて信用できるか、という話になるのなら、先進国の中で唯一成長しておらず、ダントツに生産性が低く、ダントツに貧困率の高い日本で生まれた経済理論などすべて価値のないゴミになってしまう。国の経済と、そこで得られたエビデンスは切り分けて考えるべきなのだ。
もちろん、この話も人によって受け取り方はさまざまだが、個人的には腹落ちしている。「最低賃金を引き上げたら倒産が増えて不況になる」という話には以前から胡散臭さがプンプン漂っているからだ。
例えば、今から12年前の2007年12月、改正最低賃金法が成立した。最低賃金が生活保護の受給額を下回るということが問題となって、さすがに生活保護よりは高くなるように徐々に引き上げていきましょうや、という話になったわけだが、中小企業は「それは我々に死ねということか!」と大ブーイング。当時の日経産業新聞(07年12月3日)には以下のような悲痛な声が紹介された。
「給与水準を人為的に底上げすることになり、雇用維持が難しくなる」
「採用した人材は一人前の戦力になるまでどうしても時間がかかる。最低賃金の引き上げは企業の雇用意欲を低下させる」
日本でも最低賃金引き上げは倒産に結びつかなかった
要するに、働く人たちの賃金が生活保護を下回ることよりも、「中小企業が雇用できる」ことの方が大事というのだ。なんとも釈然としないものを感じていた8ヵ月後、今度は中央最低賃金審議会が、時給687円の全国平均額を15円程度引き上げることを決定すると、さらにヒステリックな声が上がった。
日本経済新聞(08年8月6日)の「中小・零細、雇用に重し」という記事には、中小企業経営者たちの声が紹介されている。
「中小企業の倒産を誘発し、雇用に悪影響が出る可能性が高い」
「賃上げが心理的な経営圧迫につながる」
だが、事実はまったく逆だった。中小企業の倒産件数は08年の1万5646件から減少が続き、17年は8405件というレベルにまでなった。いや、倒産は減ったが、休廃業が増えているという人もいるが、別に顕著に増えているわけではなく、多くは後継者不足や販売不振が原因である。
日本においても、「最低賃金を引き上げたら倒産が増加して不況になる」ことを証明する客観的事実はどこにもない。つまり、「神話」や「思い込み」の類である可能性が高いのだ。
いずれにせよ、このアトキンソン氏が投じた問題提起に対して、「そんな話は日本に当てはまらん!」なんて島国根性丸出しで耳をふさいでいるだけでは、日本はデフレ・低成長からはいつまでも脱却できない気がする。この30年ひたすら続けてきた「日本のやり方」を続けているだけだからだ。
最低賃金を引き上げたら倒産が続出する。最低賃金で働く人はスキルがないので、一度職を失うと失業したままだ。このような主張をされる専門家の皆さんは是非とも、感覚的な話で我々素人の恐怖心を煽るのではなく、科学的根拠を示して、建設的な議論をお願いしたい。
窪田順生さんより転載 2019/09/26 06:00
2019-10-14
賃上げた韓国崩壊していない
最低賃金引き上げ「よくある誤解」をぶった斬る アトキンソン氏「徹底的にエビデンスを見よ」
https://www.msn.com/ja-jp/money/news/最低賃金引き上げ%ef%bd%a2よくある誤解%ef%bd%a3をぶった斬る-アトキンソン氏%ef%bd%a2徹底的にエビデンスを見よ%ef%bd%a3/ar-AAIu6OD?ocid=spartanntp
日本経済が「コロナ危機」にこれほど弱い根因
スペイン、イタリアと共通する「脆弱性」とは
危機への強さは「産業構造」に依存する
新型コロナウイルスの問題には、2つの側面があります。医療と経済です。医療面のことは私の専門ではありませんので、本稿では経済の側面からのみ、この問題を解説していきます。
『日本企業の勝算』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら)
日本政府の対応を見ていると、日本経済の体力に大きな懸念を覚えます。日本は経済をどこまで守れるか、大変心もとない状況なのです。
前回の記事「コロナで露呈した『日本経済の脆弱性』の根因」では、小規模事業者が多くなるほど、有事の際に負のスパイラルに陥りやすいことを説明しました。
小規模事業者は生産性が低く余裕がないため、有事の際に持ちこたえる力にはどうしても乏しくなります。すると必然的に、小規模事業者で働く労働者の比率が高い国ほど、コロナウイルスによる影響は大きくなってしまいます。
そもそも日本には小規模事業者が異常に多く、国全体の生産性を大きく低下させています。その結果、国の財政が弱体化してしまっているので、コロナウイルスの影響で今以上に負担が大きくなっても、財政出動は難しくなります。
これが日本の偽らざる実態です。日本政府はまだロックダウンには踏み切っていませんが、すでに緊急事態宣言が発せられ、多くの事業者が休業を要請されています。しかしながら、要請に応えて休業に踏み切った事業者に対しても、国としての休業補償はしないという姿勢を維持しています。
休業補償のほか、国民生活の保障に対し政府が後ろ向きである最大の理由は、日本の財政が世界最悪の状態にあるからにほかなりません。
スペイン、イタリアも産業構造が脆弱
このように財政が極めて厳しい状態に追い込まれてしまっているのは、日本だけではありません。スペインとイタリアも日本と同様に、危機的状況に直面しています。
ご存じのように、この両国は欧州の中でも突出してコロナウイルスの感染者が多く、多数の方々が亡くなってしまいました。その理由の1つは、スペインとイタリアは財政が弱く、コロナ蔓延以前から医療への投資を削らざるをえなかったので、医療崩壊が深刻化して救える命を救うことができなかったと言われています。
たしかにこの両国は財政が極めて弱く、EUに支援を強く求めています。EUとしてコロナ債を発行するべきと訴えていますが、ドイツやオランダなどが反対しています。賛成している国と反対している国を見ると、賛成しているのは生産性が低く財政が弱い国で、反対しているのは生産性が高く財政が強い国という特徴が見られます。
そして、その生産性の弱さの原因は「小規模事業者の多さにある」とされています。
スペインとイタリアの生産性は、それぞれ世界第30位と第33位です。このように低いランキングになっている状況は「スペイン病」や「イタリア病」と揶揄されています。
欧米の学会で発表された複数の論文で、小規模事業者を中心とする中小企業が全企業に占める割合が大きすぎ、企業の平均規模が小さいことが、この低い生産性の原因であるとハッキリ指摘されています。ドイツやフランスと比べてみると、その違いは明らかです。
仮に同規模の企業の生産性が各国で同じだとしても、小規模事業者の生産性は大企業の半分強程度でしかないため、小規模事業者の比率が大きくなればなるほど、国全体の生産性は当然下がります。
このような問題を抱えている国は、日本、スペイン、イタリアだけではありません。韓国、イギリス、ニュージーランド、ギリシャなどがそうです。これらの国の頭文字を並べるとSINKING、つまり「沈む」国となります。
各国とも多少の違いはありますが、小規模事業者が多いという共通点があります。それが原因で生産性は低迷し、女性の活躍は進まず、貧困率が上昇し、GINI指数で見た格差が拡大し、財政も悪化、さらには少子化も進行するという諸問題を抱えています(参考:コロナで露呈した「日本経済の脆弱性」の根因)。
中小企業が非常に多く生産性が低い国の中で、唯一財政が強いのは韓国ですが、いくつかのショックを受けて、次第に財政が悪化しています。
SINKING国はコロナショックに対抗する余力が少ない
私は、日本の人的資源が世界的に非常に高く評価されているにもかかわらず、なぜ生産性が極めて低いのかという謎の答えを、30年間ずっと探し続けてきました。
数字で見ると、2018年の国際競争力ランキングの評価では、日本は世界第5位です(世界経済フォーラムの調査、以下同)。しかし、生産性は世界第28位です。
スペインとイタリアの生産性は第30位と第33位です。一方、国際競争力では第26位と第31位です。ギリシャの生産性は世界第50位で、国際競争力は第57位です。生産性と国際競争力は、おおよそ一致しています。
世界経済フォーラムの発表によると、国際競争力ランキングとその国の所得の中央値との間には、相関係数0.82という極めて強い相関関係があると分析しています。
一方、日本、イギリス、韓国、ニュージーランドは、国際競争力ランキングと生産性の順位が大きく食い違ってしまっています。
イギリスは国際競争力ランキングでは第8位ですが、生産性は第26位で、日本と同様に2つのランキングが大きく食い違っています。
日本もイギリスも、国際競争力ランキングはスペインやイタリアより圧倒的に高いのに、生産性が同程度に低くなっています。ということは、生産性を低下させる何か決定的な類似点が存在していることが示唆されます。
その「類似点」こそ、産業構造の歪みです。何度も指摘しているとおり、日本は小さい企業が圧倒的に多いという歪みを抱えています。
イギリスのデータを見ると、労働者が大企業と小規模事業者に集中しており、中堅企業が少ないことがわかります。この産業構造の歪みが、生産性が低い原因となっています。
長期になればなるほど「財政出動」が必要になる
コロナウイルスとの戦いが短期戦ならば、各国の財政は問題にならないかもしれません。しかし長期戦になれば、どこまで企業と雇用を守ることができるかは、最終的にはどこまで財政出動ができるかにかかっています。
上の画像をクリックすると、「コロナショック」が波及する経済・社会・政治の動きを多面的にリポートした記事の一覧にジャンプします
余裕がない小規模事業者が多ければ多いほど、支援を求める企業と労働者が増えるため、その国の負担は重くなります。反面、小規模事業者が多い国ほど生産性が低くなり、財政は弱くなります。つまり、国の負担が重い国ほど、それに対応するお金が少なくなるのです。
そして日本は小規模事業者が極めて多く、財政が脆弱な国の代表格です。コロナ問題が長期化すれば、どこまで小規模事業者を守るのか、苦渋の決断を下さなければならない日が近づくのです。
2020-4-23
追補
馬淵さんの「デイ−プステ−ト」を買ってきた。 まだ。読んでいないけれども、陰謀論では片付けられないような予感がしている。林千勝さんのYoutubeも最近はみている。 グロ−バリストの大前さんに心酔していた自分であるが、最近は彼の時代は終わった感があり、自分なりに再考しなければと思っております。
ゴールドマン銀行免許取得で始まる、日本の中小企業“食い散らかし”
室伏謙一 2021/07/19 06:00 ダイヤモンドオンラインより
内閣支持率39%に下落 「ワクチンパスポート」国内利用は80%が容認 FNN世論調査
山口百恵さん、南沙織さん、郷ひろみ育てた 音楽プロデューサー酒井政利さん死去
写真はイメージです Photo:PIXTAc ダイヤモンド・オンライン 提供 写真はイメージです Photo:PIXTA
米国ウォール街を代表する投資銀行の一角であるゴールドマン・サックスが今月、日本で銀行業の免許を取得した。さほど注目されないが、彼らの動きは、菅義偉政権が執心する中小企業“再編”という名の淘汰政策に加え、銀行法改正とタイミングを一にしているのが分かる。泣く子も黙るゴールドマンの狙いはずばり、日本各地の優良中小企業を食い散らかすことではないだろうか。(室伏政策研究室代表・政策コンサルタント 室伏謙一)
ゴールドマンが“今さら”の銀行免許を取得
中小企業淘汰、銀行法改正のタイミング
ゴールドマン・サックスが、日本国内で銀行業の営業免許を取得したというニュースが、7月7日付日本経済新聞電子版(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0702D0X00C21A7000000/)で報じられたが、その後大きな反響はない。ゴールドマンといえば、外資系金融機関の代名詞のような存在であり、彼らが今さら銀行の免許と思われたかもしれない。それも無理はない。
ところが、先の通常国会で成立した銀行法改正案と、菅義偉政権が執心する中小企業淘汰政策とを併せて考えると、泣く子も黙るゴールドマンの狙いと、その危うさがよくわかる。
銀行による株式100%取得が非上場でも可能に
優良な中小企業がゴールドマンに狙われる
まず、我が国における銀行業とは何か。
銀行法第2条第2項は、「預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと」および「為替取引を行うこと」と定めている。また第4条第1項では、「銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ営むことはできない」としている。
ゴールドマンのような外国銀行の場合、日本における銀行業の本拠地となる支店を一つ定めて、内閣総理大臣の免許を受けなければならないこととされており(銀行法第47条第1項)、「外国銀行支店」という扱いとなる。
彼らの日本における主力は、銀行のような免許制ではなく、登録制で参入が容易な証券業のゴールドマン・サックス証券だ。今回、ゴールドマン・サックス・バンクUSAの日本支店設立が認められ、晴れて銀行業を営むことが可能となる。
その目的は、結論から言えば、菅政権の中小企業淘汰政策に便乗し、これを利用しようということであろう。
この政策の源流は、菅政権発足直前である昨年7月の「成長戦略フォローアップ」にあり、「事業承継、事業承継の促進」をうたったM&A推進政策という文脈では、中小企業事業承継円滑化法の改正を軸とし、中小企業成長促進法などとして着々と進められてきたものの延長線上にある。
なおゴールドマン・サックスが銀行業の免許取得に係る申請を行ったのは、2019年である。こうした一連の流れや動きを読んでの上での話であろう。
では、この先に何が待ち構えているのか?それは、日本の中小企業が、そして彼らが有する優良技術や優良事業が、事業承継や中小企業の成長、中堅企業化といった美名の下に、ズタズタに切り裂かれ、外資系ファンドやグローバル企業に食い散らかされ、売り飛ばされていく悲惨な光景である。
なぜそうしたことが言えるのか?それは、先の通常国会で閣法として提出され、衆参合わせても7時間弱の審議で可決・成立してしまった、銀行法改正案の中身を読めばよく分かる。
改正案の正式名称は「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」である。少々長いが、その心は、新型コロナショックに引っ掛けて、もっともなフリをして改正しようという魂胆だったということであろう。
むしろ、コロナに隠された真の狙いは、銀行自体の業務の範囲の拡大と、出資(議決権の取得等)の範囲の拡大である。
前者は、本来業務の収益が減少の一途をたどってきたところ、本来業務以外にも広く参入を可能とすることで、新たな収益の確保の機会を創出しようというものである。
もっとも銀行の収益の減少の原因は、資金需要の縮小であり、その原因は他でもない、デフレと緊縮財政である。したがって、銀行の収益を改善したいのであれば、国が財政支出を拡大して有効需要を創出することだ。
後者は、これまで制限されていた議決権の取得を大幅に緩和して、非上場の企業の株式であっても100%取得できるようにするというものである。これが、新たに銀行業の免許を取得する者、まさに「ゴールドマン銀行日本支店」にとって、最もうまみがあるポイントだ。
「地域活性化」隠れみのに法改正する卑怯さ
国会で「外資系金融による乗っ取り」指摘
改正案の説明資料によると、銀行は「出資を通じたハンズオン支援の拡充」の一環として、非上場の「地域活性化事業会社」に対し、議決権100%出資を可能にするとしている。
「ハンズオン支援」とは、出資先の早期の経営改善や事業再生支援、新事業開拓支援などを意味する。また「地域活性化事業会社」とは、「地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社」である。
そうは言っても、内閣府令に基づいて事業計画を策定し、地域経済活性化機構や商工会議所、弁護士や会計士、税理士、さらにはコンサルティング会社(銀行の子会社や関連会社であるものを除く)が関与していれば、ほとんどの企業がこの「地域活性化事業会社」になりうる。
つまり、地域活性化事業とは名ばかりであり、非上場企業の株式を100%取得できるというところが一番のポイントであることをごまかすため、煙に巻くための修飾語ということだろう。なんと、卑怯(ひきょう)なことか。
この点に対しては、法案が審議された4月23日の衆議院財務金融委員会(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009520420210423013.htm)で、立憲民主党の長谷川嘉一衆議院議員が、核心を突いた強い懸念を表明している。
「非上場であれば、今までであれば上場していないわけですから買収されないのが通常であったわけですが、非上場であっても議決権、100%出資が可能になるということになるわけであり、銀行が融資状況などを起点として非上場の中小企業を子会社化することもできるということを意味するというふうに私は認識をしております」
「このことは、中小企業にとっては、頼りになる銀行が、頼りにならないどころか、買収サイドになってしまう可能性もあるわけであります。こうした改正が行われるということに対して強い危惧を覚えているところであります」
そして、外資系銀行による中小企業の買収についても懸念を表明し、今回の改正の対象に彼らが含まれるのかについても質問した。だが、金融庁の官僚の答弁は、
「現在、日本では外国の法人が主要株主になっている銀行が存在するというふうに考えております」
と、木で鼻をくくったようなものだった。外国銀行であっても、外国銀行支店として銀行業の免許を取得していれば対象になると素直に答弁すればいいのに、余程やましいところがあるのだろう。かえって長谷川議員の懸念はごもっともだと答弁しているようなものだ。
これに対して長谷川議員は、次のように意見を述べて、再度、懸念を強調した。
「外資の銀行が含まれるのであれば、言葉は悪いんですが、外資銀行が我が国の魅力ある中小企業を乗っ取ることが可能になるということを意味するということになります。このことを併せて申し添えさせていただきます」
ゴールドマンによる銀行業免許の取得の最大の目的は、まさにここにあるということだろうし、長谷川議員はそれを十分理解していたということだ。
だが、こうした指摘は共産党を除く与野党の賛成による可決という「風」の中にかき消されてしまった。
なお自民党の石川昭政衆院議員も、与党議員としてはギリギリの線で「確認」という形で質問し、指摘していたことを付記しておく。同議員は「日本の未来を考える勉強会」の会員であり、自民党内の反緊縮、反構造改革勢力の一人、良識派議員の一人である。
中国系銀行5行もすでに免許を取得済み
日経以外の大手メディアも報じない「罪」
現在、外国銀行支店として銀行業の免許を取得しているのは、本年2月22日時点の数値で55行であり、ゴールドマンがその一角に加わったことで56行となった。その中には中国系銀行5行も含まれている。
改正銀行法は11月中頃までには施行されることになる(本稿執筆段階で施行日は確認できず)。そうなれば、先ほどの長谷川議員が懸念する通り、邦銀と言わず外資系と言わず、支援の名を借りた買収合戦が各地で繰り広げられることになりかねない。とりわけ、外資系でも辣腕(らつわん)で知られるゴールドマンだ。彼らの勢いは、邦銀のそれをはるかに上回るだろう。
そんな状況を放置すれば、地方の中小企業は外資系銀行の食い物にされ、地域経済、地域社会は破壊され、雇用も失われて、地域活性化や地方創生どころではなくなっていくだろう。
今回の銀行法改正、そしてゴールドマンによる銀行業の免許取得は、我が国社会経済に多大な影響を与えうるものなのである。だが、多くの人がこのことに気づいていないし、そもそも知らない人があまりにも多いようだ。日経以外の大手メディアが全くと言っていいほど、このことを報道しなかったことによるところが大きいだろう。
加えて、国民を代表する国会議員が、資料やレクチャーの要求を通じ、衆参両院事務局の調査室や国会図書館を通じて、この問題を調べ、勉強することは十分可能であったにもかかわらず、それをしなかった。そうした勉強しない議員たちの「罪」も大きいといえる。
改正案は成立し、施行に向けた準備が着々と行われている。今から廃案にすることは当然出来ないが、将来的に、再改正によって内容を削り、元に戻すことは不可能ではない。しかしそのためには、今回の改正の問題点をより多くの人に知ってもらい、より多くの国会議員に理解してもらって、懸念や反対の声を高め、広げていくことが重要だ。
本稿が、その一助となれば幸いである。
2021-7-20